|
小さな液晶画面に映った水瀬伊織は、とても可愛らしく、清純で、可憐に見えた。
カシャッ――、カシャッ――。
律儀にシャッターの音に似せた合成音が響く。
3枚目――、4枚目――。
伊織は机に両肘を突き、両手で頬を包むようにしながら、上目遣いでレンズを覗く。
小さく尖らせた唇には、しっかりとピンクのラインが引いてある。
「伊織ちゃん……カワイイ」
思わず口をついて出たその声を合図に、伊織はアイドルらしい表情を崩す。
「当たり前でしょう。モデルが最高なら、誰が撮っても良い写真になるのよ」
伊織は、カメラのレンズ越しに撮影者、萩原雪歩に世界の真理を告げる。
「うん。すごく素敵な写真だよ」
雪歩は、液晶の中の伊織の笑顔を見詰めていた。
今にも泣き出しそうな笑顔で、見詰めていた。

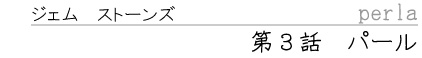
4月のある日。午前10時。765プロダクションの小会議室。
雪歩と伊織は学校の制服姿のまま、カメラマンとモデルに分かれていた。
――次の撮影の為に、かわいく見えるポーズを教えて欲しい。
それがただの口実である事くらい、伊織には分かっていた。
仮に誰かに指示をされたのだとしても、伊織と同じようなポーズをとる事自体が、雪歩にとっては苦痛なはずだ。
――伊織ちゃんだからかわいく見えるんだよぉ。
普段の雪歩なら、そう言って嫌がるはずだ。だから、今日の雪歩はどこかおかしい。
自分と他人の間に明確な線を引くのが、雪歩の性分だ。
自分は、他人とは違う。
それは、ダメな自分を許す唯一の方法であり、弱い自分を守る唯一の手段――。
「あー、もう。バカバカしい」
雪歩には聞こえないように小声で言った。
その程度の分別はあったし、けれど、何も言わずにはいられなかった。
「雪歩、交代よ。今度は私が撮ってあげる」
カメラを構える水瀬伊織。
モデル、萩原雪歩。
最初の指示。
「とりあえず、上着脱いでちょうだい」
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
「伊織ちゃん、ヒドいよぉ……」
撮影会を終えた雪歩は椅子に座ったままグッタリと机に伏せ、組んだ両腕の中に顔をうずめていた。
「ボタンの1つや2つで文句言わないでよね。別にブラが写った訳じゃないんだし」
「私、かわいく見えるポーズって言ったんだよ!?」
ほんの少しだけ顔を上げ、訴えるような視線を送る雪歩。
「椅子に足掛けたポーズなんて顔が真っ赤になってて可愛かったわよ」
「それは意味がちがうよぉー!」
ふえーん、と、まるでマンガのように泣く雪歩を見て、伊織が大きくため息をついた。
萩原雪歩は、良く言えば繊細だ。悪く言えば臆病で、度胸が無く、根性が無く、勇気が無い。
その立ち居振る舞いは、見る者の心を大きく揺らす。
守ってやりたいと思うか、いじめてやりたいと思うかのどちらかだ。
水瀬伊織はかろうじて前者だったが、そろそろ分水嶺を越えようとしている。
「で、結局何がしたい訳? いい加減切り出さないなら私も戻るけど?」
撮影に見せかけて、雪歩のデジカメのメモリーは確認している。
悪いとは思うが、それ以上に大事な問題を解決する為だから、許されるはずだ。
その、撮影済みの写真の数々が、バラバラだった情報を一本の線で結んでいた。
伊織は、あの、えっと、と言葉に迷う雪歩にデジカメを返す。
「『歌を上手く歌うには、姿勢も大事なんだよね』」
伊織は、雪歩の話し方と声を真似して言った。
「そう言われたって、千早は喜んでたわよ。だから、自分が歌う姿の写真を撮らせたって」
そんな話を聞いたのは、3日ほど前の事だった。
そして、同じような話を、真からも、美希からも聞いた。真はダンス。美希はポーズ。
「真と、美希と、後は誰の写真を撮ったの? 私の後は、誰を撮るつもり?」
伊織には、責める気も問い詰める気もない。答を知りたい訳でもない。ただの確認作業。
「最後に小鳥か社長に頼んで、全員の集合写真でも撮るつもり?」
ただ、雪歩の表情は硬くなり、視線は足元に落ちていた。
「まるで、卒業式直前の女子中学生みたいじゃない。一体、何の思い出作り?」
雪歩は、ただまっすぐ伊織を見詰めていた。
今にも泣き出しそうな笑顔で、見詰めていた。
「私は、みんなとは違うから……」
ステージの失敗とその後の収録でのミスが重なった、というありがちな話。
問題なのは、その後のプロデューサーの慰めも、大きく的を外していた点だ。
――大丈夫、雪歩だってすぐ、みんなみたいになれるさ!
伊織は、軽いめまいを感じた。
「あのバカプロデューサー、何にも分かっちゃいないんだから」
「え、伊織ちゃん……?」
「雪歩!」
「はいっ!?」
伊織はビシッと音が出そうな勢いで雪歩の鼻先に指を突き付ける。
椅子に座ったままの雪歩を見下ろしながら、射抜くような視線を向ける。
「アンタが私みたいになれると思う?」
「む、無理……だよね?」
「当たり前でしょ!」
「春香が千早みたいなシンガーになれると思う? 千早や真があずさみたいなグラマーになれると思う?」
「可能性、ゼロじゃないと思うけど――」
「ゼロよ。無理。不可能。ありえないわ」
伊織はバッサリと斬って捨て、雪歩は、会議室が本当に2人きりかどうか確かめる。
「『誰か』みたいになってどうすんのよ。そんな二番煎じ、ファンが喜ぶと思う!? 自分に満足できる?」
伊織は矢継ぎ早に言葉を紡ぐ。
「ナンバーワンよりオンリーワンなんてふぬけた考え方、私は絶ッ対に認めないわよ」
腕を組み、視線を外さずに、伊織は雪歩に、逃げる事を許さなかった。
「自分は他人と違うなんて当たり前なのよ。それを理由にナンバーワンを目指さないのは、ただの逃げよ」
雪歩は、黙ってうつむいていた。
けれどそれは、嵐をやり過ごす為の自己防衛ではなく、伊織の言葉を噛み締め、理解する為の時間だ。
伊織はその雪歩が視線を上げるのを待って、視線を合わせてゆっくりと伝える。
「こんな事言うの、1回だけだからね」
雪歩は、小さく頷く。
「アンタは真珠よ」
「真珠……?」
雪歩の目に、少しだけ力が戻っていた。
伊織は椅子を1つ引っ張り出すと、雪歩の前に座り、足を組む。
「宝石は原石から生まれるわ。岩の中から切り出され、削られ、磨かれ、宝石になるの」
ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド、ガーネット、アメジスト――伊織は指折り数え上げる。
「でも、例外もあるわ。それが、パール」
パール、真珠、と雪歩は呟いた。小さな、けれどしっかりした声だった。
「雪歩は宝石の原石と自分を見比べて、自分はちっぽけだと思うかもしれない。でも雪歩はまだ核なのよ」
「核?」
「他の石が磨かれて輝きを増していくんだとしたら、アンタはゆっくり時間をかけて、光をまとうの」
伊織の声はどこまでも澄んでいて、表情はいつになく優しい。
「他の石は、輝きを増す為に小さくなるけど、真珠は輝きを増す為に大きくなるのよ」
雪歩はその声を、自分の胸に刻んでいく。
「不安な時は、貝の殻に篭ったって構わない。だったら、その中でも輝きを集め続けなさい」
とても大事な言葉に思えた。自分に届けられた、とても大切な想いだと感じた。
「真珠、私、結構好きだなぁ」
「雪歩にピッタリよ。真珠は、他の全ての宝石に勝る点があるって事、知ってる?」
首を横に振る雪歩に向かって、伊織はニッと笑って見せた。
「真珠だけが、冠婚葬祭、いつだって身に付ける事を許されるのよ」
ああ、と息をつく雪歩の表情に、伊織は、伝わった事を確信していた。
誰にも勝る、飛び抜けた魅力は見えにくいかもしれないけれど。
今はまだ、人と比べて落ち込む事があるかもしれないけれど。
でもきっと、今に雪歩は、どんな年齢の男女にも愛されるアイドルになる。
どんな番組にでも、どんなCMでも活躍できて、どんな歌でも歌えるアイドルになる。
伊織は、椅子から立ち上がると、少し頬を赤くした雪歩の肩に、手を置いた。
「アンタの貝殻は、ここなんだからね。立派な真珠になるまでは、ここから出るんじゃないわよ!」
そのまま、伊織は会議室を出る。
その背中に、雪歩の声が届いた。
「……うん。伊織ちゃん、ありがとう」
雪歩が会議室から出たのは、その15分後。
彼女が最初に踏み出した1歩は、プロデューサーに電話を掛ける事だった。
【End】
|