|
<< プレゼント >>
プロデューサーの業務は多岐に富む。
実際の所、やっと中堅と言える規模になったばかりの765プロにはマネージャーがおらず、アイドルの
スケジュール管理やレッスンの立会いなども全て、プロデューサーが兼務する格好だった。
そして毎週金曜の定例行事は、事務所に届いたファンレターとプレゼントの確認と、分類である。
「さて、と。パパッとやっちゃいますか」
そんなプロデューサーに声をかけたのは、765プロ所属のDランクアイドル、秋月律子だった。律子は
デビューして約半年だが、波に乗り掛けた所で小さなスキャンダルに巻き込まれるような事が多く、あと
一歩ブレイクできずにいた。実力相応のステージに立たせることが出来ない現状をプロデューサーは嘆いて
いるが、当の律子はさして気にせず、時間がある時はプロデューサーのアシスタントのような仕事をしている。
「こうしてファンレターやプレゼントを見てると、誰がどんな層に人気があるのか、よく分かりますよね」
「これでみんなのやる気が上がれば、ファンの皆様にも喜んでもらえるし、いい循環だよ」
プロデューサーは、一時的に作業スペースとなった休憩コーナーからファンレターBOXを手に取り、隣の
デスクに陣取った。ファンレターは、全てプロデューサーが事前に目を通す事にしている。時折、本人に
渡すには不適切な内容の手紙があるからで、それは、できれば律子にも見せたくないと思っていた。
作業スペースに残った律子の役割は、プレゼントのチェックだった。手作りのお菓子などは、衛生上の
問題などがあって本人には渡せないのでスタッフ向けのおやつBOXに入れられる事になる。
市販品も、パッケージに穴が開いていたりしないかを確認するのだが、それは実家の手伝いでもやっていた
内容なので、律子の得意分野だった。
プロデューサーは手早く宛名毎にファンレターを分類し、細いペーパーナイフを使ってなるべく綺麗に開封し、
それらの文面に目を通す。通数で言えば、トップはあずさ。それを追う格好で雪歩が続く。もう少しすれば、
きっと春香と千早宛のファンレターが増える事だろう。2人はデュオとして、再来週、デビューする事が
決まっている。今は毎日がレッスンで、事務所にはいない事がほとんどだった。
「うわー、あの子達の作戦通りねぇ」
その声に振り向いたプロデューサーが律子の手元を覗き込む。律子が開けた箱には、最新型の携帯ゲーム機
本体が2台入っていた。先週放映されたバラエティ番組で、亜美が欲しいからお金を貯めている、と発言した
ものだった。
『でね、でね、亜美ね、2台買おうと思ってるんだ! 2台あれば収録の合間に、1台をADのお姉ちゃんに
貸してあげて、2人で対戦とかできるっしょ!? しっかり腕みがかないと、小学校で遅れちゃうからね!』
亜美は、お小遣いを一円たりとも貯金していない。そしてもちろん、そのもう1台は真美のものになるのだ。
ファンの人に嘘をついちゃダメだろう、と注意したプロデューサーは、じゃあ真美は双海真美でーす、って自己
紹介しなきゃね! という真美の発言でそれ以上文句が言えなくなってしまった。
「すごいな。オンエアの次の週には来ちゃうんだもんな」
プロデューサーは律子に背を向けてファンレターの確認作業に戻る。律子は内容物を確認しながら、それらの
内容をプロデューサーに報告していく。
「雪歩宛。差出人が京都市の達筆なお爺さん。宇治茶の詰め合わせ。半分事務所にもらえないかしら」
「真宛。差出人が、お! 神奈川の男性。中身は、アクアマリンのペンダント! 真、本気で喜びそうね」
「あずささん宛。差出人が、こちらも神奈川の9歳の女の子。中身は――」
箱の中身が、「ワン!」と吠えた。
<< 仔犬のメイ >>
あずさお姉さんへ
『三浦あずさのまちぶら』いつもみています。
この前、ウチのサツキが子犬を産みました。
あずさお姉さんが入ったペットショップで、
「かってみたいわー」と言っていたトイプードルです。
あずさお姉さんにかってもらえたらこの子も幸せです。
かわいがってあげて下さい。
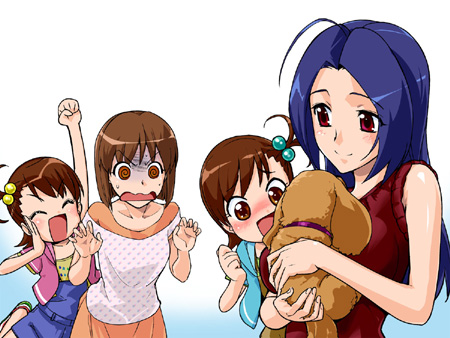
「あずさお姉ちゃん! 次、真美にも抱っこさせてよー!」
あずさの胸に抱かれた子犬を見て、真美が目を輝かせている。
「じゃ、ゆきぴょんの次が亜美ねー!」
「え? ええっ!? わ、私はいいよぉー」
亜美に煽られた雪歩が目を白黒させながら逃げ腰になり、ジリジリと後退してゆく。
「亜美、分かっててそういう事を言うもんじゃないわよ」
注意した伊織は目に掛かる前髪を左右に分けようとするが、しなやかにトリートメントされた艶のある髪は
まっすぐストレートに下りてきてしまう。さっきまでいつも通り伊織の髪をまとめていたリボンは、今や子犬
のものだ。
「首輪が無いままうっかり迷子になって、保健所にでも連れて行かれたら可哀想じゃない」
伊織はそう言って、子犬の首にそっとリボンを巻いてやった。
子犬は『メイ』と名付けられ、日中はオフィス内で面倒を見て、夜はあずさが連れて帰る事になった。
翌日の土曜日も、765プロの主役はメイだった。
今日あずさはオフの予定だったので事務所に顔を出す必要は無かったのだが、亜美と真美がメイを気に入って
しまい、どうしても事務所に連れて来て欲しいと泣き付いていた。あずさはそれを無視する事ができなかった。
実際にメイの仕草は可愛らしく、誰にでも擦り寄っていく人懐っこさのせいで、事務所内でもすぐに人気者に
なっていた。ただ1人、その人懐っこさのせいで迷惑をしている少女もいるのだが……。
「ちょっと亜美! 今日はダンスレッスンでしょ。着替えの準備終わってるの?」
律子が、メイと遊んでいた亜美を注意する。まだ弱小で、渋谷駅に程近い雑居ビルの3階にある765プロの
に、レッスンができるようなスペースは無い。だから、レッスンは全て外のスタジオを借りて行っている。
「あーあ、真美はいいなぁー。メイとずーっと遊んでられて」
「そんな事ないよ! 昨日は真美がボーカルレッスンだったじゃーん」
メイを抱きながら真美が言う。亜美はそれでも未練がましい視線で真美とメイを見つめながら、
「りっちゃんの意地悪メガネ! 鬼メガネ!」
と捨て台詞を残して、バッグを背負って出て行った。律子は、ため息をつくでもなく書類のチェックに戻る。
――はいはい。どうせお局様ポジションですよー。
律子はため息混じりに、自分の机の上に並んだクイズ本の数々を片付けていく。最近クイズ番組に出演する
事の多い律子が研究用に買っている資料だが、みんなの暇つぶしに使われていた。
やがて、亜美と入れ違いにやって来たのは真だった。真はみんなに挨拶をすると、律子の隣にやってくる。
「律子、おはよう。雪歩はまだ来てないの?」
「おはよう、真。あー、この状態だからね。屋上だと思うから、一緒にいてやってもらえる?」
この状態、が何を指すのか、真はすぐに理解した。
「了解。じゃ、ちょっと上に行ってるから。プロデューサー来たら携帯鳴らして」
「はいはい。じゃ事務所じゃなくて私の個人携帯からかけるわね」
差し出される真の拳。軽く合わせる律子。真は満足そうに、オフィスから出て行った。
真が屋上に上がると、鉄柵にもたれ掛かるようにして雪歩が俯いていた。
「雪歩、大丈夫ー?」
真が大きな歩幅で雪歩の方へ歩み寄ると、雪歩は真の胸に飛び込んだ。
「ふぇーん。真ちゃーん」
真は雪歩の背中をポンポンと叩くと、感じている事を全部話してごらん、と微笑んだ。
雪歩は、どうしても犬を怖がってしまう自分が嫌だ、と訴えた。真は、組んだ両腕を鉄柵に乗せ、隣の、
同じ姿勢の雪歩にゆっくりと語りかける。無理はしなくていいよ、その気持ちがあれば大丈夫、みんなも
分かってくれるよ、と。
2人の視界には、雑然としたビルの森が映っていた。その谷底のような一画が、小さな公園になっている。
きっと、もう少しであずささんと真美がメイを連れて散歩にいくだろう。それまでは、雪歩と色々なお喋りを
しよう、と真は思った。
その公園には、スーツ姿のサラリーマン風の男が数人いるだけだった。
<< 事件 >>
メイが事務所にやって来て、もう4日が経っていた。
初日、律子が強行した動物病院での診察の時は大暴れだったらしいが、事務所に来てからは総じて大人しく、
吠えることも無い。特にあずさと亜美真美に対する懐き方は周囲の人間から見ても微笑ましいものだった。
亜美と真美がビジュアルレッスンに行くという事で外出すると、あずさの午後はぽっかりと空いてしまった。
スカートの裾を噛んで外に連れて行けと催促するメイを連れて、あずさは狭い公園にやってくる。奥のベンチで
は少し遅めの昼食だろうか、スーツ姿のサラリーマンが2人、コンビニのパンやおにぎりを食べていた。
あずさは、小さなボールを取り出すと、それを公園の、ベンチから遠い方へと投げた。
――Cast a spell on me! Cast a special spell on me!
真の携帯が震えた。あずさの外出――つまり事務所にもう犬はいないという事――を伝える律子からの合図
だった。真は一度、雪歩と視線を交わし、頷いてから電話に出る。
「なんで出るのよ」
真が電話に出ると、電話を掛けた側の律子が不満そうに言った。
「掛かってきた電話に出て文句言われるとは思わなかったなあ」
「だって出る必要ないでしょ? あずささん、もう出たわよ」
「ああ、知ってる。ちょうどここからも見えたよ」
真は視線を公園のあずささんとメイに向ける。ちょうど、ボール遊びの真っ最中だった。
「雪歩と相談したんだけど、ちょっとここからあずささん達を見学してから降りるよ」
「ふぅん。ま、いいんじゃない。迷子になりそうだったら、上からナビしてあげてね」
律子は素っ気無く電話を切ってしまったが、真には、なんとなく律子の表情が見えていた。
雪歩は、公園で遊ぶメイを見ていた。その動きは可愛いと思うし、仕草が愛くるしいというのも理解できる。
でも、目の前に立つと怖くて仕方が無い。言葉が通じないのが怖い。次の動きが分からないのが怖い。
――でも、他の犬に比べたら……
雪歩は、みんなが可愛がるメイを可愛いと思える、頭を撫でてやれる自分になりたいと思っていた。
「あれ? 三浦あずささん?」
公園を出ようとした時、白いスーツ姿の男に声を掛けられた。金髪に近い明るい髪を細いカチューシャで
押さえた、良く日に焼けたホストのような外見の男だった。
「俺、大ファンなんですよ。握手してもらえませんか?」
男は、シルバーのリングがいくつも光る右手を差し出す。あずさは一瞬躊躇したが、抱いていたメイを
そっと地面に下ろすと、右手で握手に応え、そっと左手を重ねた。男は大喜びし、そして、
「あ、そうだ! せっかくだからちょっと歌ってみて下さいよ!」
と、大きく手を広げてあずさの前に立ち、あずさの顔を下から覗き込むようにしてはやし立てる。あずさは
何とか笑顔を保とうとするが、どうしても困ったような苦笑になってしまう。
「あ、あの、私、そろそろ事務所に戻らないと――」
「いいじゃないッスか。どうせ近いんでしょ? 俺、あずささんの『Here we go!!』大好きなんですよ!」
男は、両腕を広げたまま公園の出口を塞ぎ、まるで困り顔をするあずさの様子を楽しむかのようにヘラヘラと
笑いながら、その曲のサビを歌い始める。
「Here we go〜、Here we go、ランデ〜ブ〜!」
やめてください、とあずさが男から顔を背けた瞬間、メイが、跳んだ。
「真ちゃん!」
雪歩の悲鳴に似た声を聞きながら、真はその事件の一部始終を見ていた。
小さなメイが全身のバネを使って跳躍し、男の、白いスーツの上からその右腕に噛み付いた。慌ててメイを
なだめようとするあずさの声を無視して、男の腕にぶら下がったままのメイは首を振り、体を揺らす。
事務所ビルの屋上の2人の目から見ても、状況は明らかだった。
男のスーツに、真っ赤な染みが広がっていた。
<< 訪問者達 >>
律子は取り乱すあずさを落ち着かせ、男から受け取ったという黒い名刺を見ながらキーボードを操作した。
「カツラギ、ショウ――と」
桂木翔。それが、男の名前だった。株式会社ルミナウェイブ、代表取締役社長。検索の結果出てきた顔写真は
どれも軽薄そうで、お世辞にも、ビジネスを一緒にやりたいと思うような相手ではない。
律子は続けて、企業情報を検索する。株式会社の体はとっているが、上場はしていないらしい。
「律子さん、あの、私達、どうなっちゃうんでしょうか……」
メイを抱いたあずさが、不安げに律子の隣に座った。男はあずさに名刺を渡すと、その時公園にいた2人の
サラリーマンの目撃証言と連絡先だけを聞いて病院に向かった。その様子の一部始終は屋上から真と雪歩が
見ていたし、携帯電話を通じて律子も実況中継を聞いていた。律子が公園に着いた時には桂木の姿は無く、
そこにはポロポロと涙を流すあずさと、まるで褒めてくれと言わんばかりに胸を張って座るメイがいた。
株式会社ルミナウェイブ。主な事業は携帯サイトのコンテンツ制作とそのサービス運営らしい。
「普通に考えれば、謝罪と治療費と、いくらかの慰謝料だと思うんですけど――、ちょっと読めないんです」
律子の胸には、拭い去れない不安があった。そして、それはすぐに的中する事となる。
翌々日、水曜、13時。それは、突然の訪問者だった。
「待って下さい! そんなの、横暴です!」
悲痛なあずさの声に、グレーのスーツの男性はこめかみを押さえる。
「横暴って、いや、気持ちは分かるけど、しょうがないんですよ。こっちも、訴えがあった以上はねぇ」
2人組の男は、保健所の職員だった。応接スペースであずさに対していくつかの質問をし、あずさはそれを
事実だと認めた。結果、メイは、保健所に収容される事となった。遅まきながら事態を理解したあずさだったが、
しかし保健所側は被害を訴えた男性――桂木からのヒアリングも終えていたし、桂木から提供のあった目撃者の
連絡先へも連絡を入れ、あずさが子犬を公園で遊ばせる際にリードやハーネスを付けず、放して自由にさせて
いた事等も確認済みだった。
「子犬だからって、放しちゃったらダメですよ。犬は何が原因で人を噛むか分からないんだから」
責任はあんたにある――それが、保健所の側の言い分であり、あずさも反論はできなかった。見ていて痛々しい
くらいに、あずさは保健所の職員に頭を下げる。けれど、それでも男の片方があずさをなだめ、抑えて、もう片方
の男が子犬に睡眠薬入りのビーフジャーキーを食べさせている。メイちゃん、ダメよ、後でもっと美味しいものを
食べさせてあげるから――そんな、涙声のあずさの叫びを聞きながら、事務所の仲間は何も出来なかった。
その日の14時25分。メイは、所轄の保健所に収監された。
まるで抜け殻のようにソファに座るあずさの前に、律子が立った。
「どうしたいですか?」
あずさは、消え入るような声で呟いた。
「私、お引越ししようと思ってたんです。今のマンションもペット飼えるんですけど、もっと、専用の……」
それは、律子の問いに対する回答になっていなかった。思考停止。あるいは現実逃避か。
あずさの頬は涙で濡れ、ニットの胸には濃い青の染みがいくつも出来ていた。
律子は踵を返し、自分のデスクに座る。精神の均衡、という意味で言えば、限界だ。
「あの、律子さん。どうにかならないんでしょうか?」
律子は、小鳥の声を聞いていたが、特に返事はしなかった。キーボードを叩き、いくつかの情報を確認する。
「里親制度みたいなの、ありますよね? 例えば、保健所に行って、私がメイちゃんの里親に――」
「無理です。今回の収監理由が人を噛んだ事による傷害罪と危険動物指定ですから、被害の訴えが取り下げられ
ない限り里親の引き取りは認められません」
「そんな……」
律子は役に立ちそうな情報を拾い集め、HDDの中に蓄えていく。フォルダ名は『for A』。
「待ちましょう。病院に行ったら連絡すると言ったきり連絡してこない、被害者からの連絡を」
狂犬病予防法に従えば、殺処分までの猶予は3日。だが行政区の条例により、殺処分までは7日の観察期間を
設けると定められていた。タイムリミットは来週の水曜日。
おそらく相手はそれを知っている。
律子はあずさのスケジュールを確認する。しばらくはレッスン中心だが、週明け火曜日には朗読劇の仕事が
あり、その翌週には難関オーディションのひとつ、『歌姫楽園』が控えていた。
――三浦あずさは、“こんな事” で足止めをされていいアイドルではない。
<< 残された道 >>
『渋谷洞窟』という名のカフェダイニング。金曜日の15時。それが、桂木の指定だった。
当初は三浦あずさ1人で来るようにという指示だったが、さすがにそれは出来ないとプロデューサーが交渉
し、プロデューサーとあずさの2人で向かう事となった。
道玄坂下のY字路を左に進み、ロッテリアの先の角を左に入ったビルの2階にその店はある。店内は石と土の
イメージで統一された落ち着いた空間で、照明効果と相まって、まさに隠れ家的な空間だった。Pとあずさは、
奥のBOX席に通される。店の本来の開店時刻は17時なので、他に客はいなかった。
「ああ、ご足労頂き申し訳ありません。ここは知人の店でね。ほら、あまり人目に付きたくないでしょう?」
桂木は先に座っていた。紫色のシルクシャツに黒のスラックスという姿。耳や首周りにはシルバーが目立つ。
「この度は、うちの三浦あずさの飼い犬が大変失礼致しました」
プロデューサーは真っ先に頭を下げ、桂木のいえいえ、という声が聞こえるまでその姿勢でいた。
「座ってください。私もヒマじゃないんで、話を、シンプルにしましょう」
桂木は向かいに座ったプロデューサーに病院の領収書を差し出す。金額は2万6千円。不自然な額ではない。
「私は三浦さんのファンなんで、慰謝料とかは要りません。治療費と同額、振り込んでください」
「あ、いえでも、そういう訳には……」
プロデューサーは、とっさに口を開いていた。高木社長とは、10万以下で済めば御の字だという話をしていた。
「それとは別の話なんですがね」
桂木が笑顔で言った。
「今度、うちの携帯コンテンツで『迷えるアナタの占星術』という占いのサイトをローンチするんです」
桂木は、足元のバッグからA4サイズのクリアファイルを取り出し、それをプロデューサーに差し出した。
「今回お知り合いになれたのも何かのご縁ですから、ぜひ、三浦さんと広告契約を結ばせていただけないかと
思うんですが、こちらとしてもそれほど広告費が取れないので、その限られた広告費の中で精一杯の条件を
提示してみました。一度、ご検討ください」
薄っぺらなクリアファイルには、企画書と契約書、そして、PRプランの概要が挟んであった。
「あ、あの! 本当に、すみませんでした!」
あずさが口を開き、深く頭を下げる。
「もう、公園で放したりしません。しっかり管理します。だから、あの子を助けて下さい!」
桂木は笑いながらあずさの顔を上げさせ、その目に涙が浮かんでいるのを見て、大きく首を振る。
「三浦さん、私は保健所の人に聞かれて、事実を言っただけなんですよ。あの子犬が死んでも、私には何の得も
無いし、傷が治る訳でもない。だから、ビジネスパートナーの飼ってる子犬なら、すぐにでも被害届けを取り
下げますよ」
両手を大きく広げ、芝居がかった言い方で、桂木はあごを上げて2人を見下す。
「ただ、それが赤の他人の飼い犬なら、どんな死に方しようが知ったこっちゃ無いですけどね」
桂木は、あずさの表情の変化を確認し、次いでプロデューサーへ視線を向けた。
「そうそう、そのPRプラン読んでみて下さい。あの子犬にも出番があるので、もしそのPRプランが採用され
れば、急いであの子犬を助けに行かないといけないんですよねー」
プロデューサーとあずさは、運ばれてきたアイスコーヒーに手を付ける事無く、渡された資料を手に席を立つ。
「週明け、月曜の17時に事務所へ電話しますよ。それまでに決めておいて下さい。色々と」
桂木はじっとあずさの目を見据えたまま、またお会いしましょう、とその右手を振った。
高木は、その契約書を見てため息をつく。
「これでは、完全にタダ働きではないかね」
プロデューサーは、PRプランの概要を開いて見せる。そこには、初回の記者発表の内容が記されていた。
「占いに従って桂木が公園に行ったら、逃げた犬を探すあずささんと偶然出会い、2人で協力して犬を発見した
事になっています。そこの携帯サイトの『尋ね人占い』で」
「……まるで、婚約の記者会見だね。2人の馴れ初めを聞いているようだ」
「十中八九、そういう噂は、流れるでしょうね」
ふむ、と高木は頭を抱えた。どんな理由を付けた所で、三浦あずさに子犬を諦めさせる手段など見つかり
そうにない。ともすれば、移籍、引退すら選択してしまうだろう、とは容易に予想できていた。
壁一枚隔てた事務所では、三浦あずさが頭を抱えていた。メイを見殺しには出来ない。けれど、それが事務所
にどれだけ迷惑を掛け、自分のアイドルとしての将来にどれだけの影を落とすか、あずさにはただ漠然と想像
する事しかできなかった。
状況を把握した小鳥や真、雪歩や亜美があずさを心配して周りを囲み、口々に声を掛ける中、律子は用事が
あるのでお先に失礼します、と事務所から出て行った。
「りっちゃんってばホントにハクジョーだよねーっ!」
わざと聞こえるように言った亜美の声が、扉越しに律子の背中に届いたが、律子は足を止めなかった。
16時。約束の時間までは、あと1時間あった。
<< 律子と男 >>
渋谷駅から、渋谷エクセルホテル東急と東急プラザの間を抜け、渋谷マークシティを右手に見るビルの2階に、
その店はある。『トウキョウサロナードカフェ:ダブ』――アジアンエスニックとヨーロピアンモダンの調和した
その店の奥、L字型のソファに、1人の男が座っていた。短く揃えた髪を中央で分け、身体はイタリアブランドの
三つ釦スーツに包んでいる。真面目な銀行員といった雰囲気。歳は20代半ばから後半といった所だ。
男は銀色のメタルフレームの眼鏡のズレをそっと直し、腕時計に目をやった。17時15分。指定された時間は
過ぎていた。珍しい事もあるものですね、と呟きながら、男はテーブルのグレープフルーツジュースを一口飲んだ。
さらに5分ほど経った頃、入り口から入ってくる少女がいた。スタッフの問い掛けに、男の座るソファを指し
示すとアイスカフェモカを注文し、そのまま真っ直ぐに店の奥まで足を進める。
「すみません。少し、手間取ってしまって」
「珍しいですね。秋月さんが時間に遅れるなんて」
律子はL字型のソファの反対側へ座り、右手に掛けていた夏場には不似合いな黒いウールのコートを丸めると、
テーブルのメニューを開いて言った。
「『生ハムとグリーンサラダ・ノワゼットドレッシング』と、『ピクルスとオリーブの盛り合わせ』かな。あなたは?」
「えっと、では『タコとオリーブのオニオンレモンソース和え』と、『なすとミートソースのグラタン・ギリシア風』を」
手を挙げ、手短に注文を済ませると、律子は軽く礼を言ってから事情を説明する。移動中にプロデューサーに
電話を掛けて聞き出した、契約内容や相手のPRプランの概要も合わせて伝える。
「状況を考えると、相手側はフォーカード、って所でしょうか」
男はスーツの内側から小さな黒革張りの手帳を取り出すと、表紙裏のカレンダーを見る。それでも自分が呼び
出されたという事は、どこかに逆転の目があるという事なのだろう、と理解していた。
「『三浦あずさの街ぶら』は、東京なら日曜の15時放送だけど、神奈川では日曜の深夜23時45分からの放送よ。
9歳の女の子が見ているにしては、ちょっと不自然じゃない?」
「確かに。ダンボールに詰めて子犬を送りつけるなんてのも、子供じゃ無理ですよね」
運ばれてきた4つの皿をテーブルに並べ、2人は端から順に味わっていく。ノワゼットドレッシングはヘーゼル
ナッツをベースにしたドレッシングで、レタスやクレソンとの相性が抜群で、律子の大好物の一つだった。
「大体把握できましたので、ここからはビジネスの話になるんですが」
「どんな方向性がご希望?」
男はフォークで薄造りの蛸とオリーブを刺しながらいくつか口にする。
「天海春香と如月千早のデビュー」
「論外。期待の新人だもの」
「水瀬伊織のお家騒動」
「無し。今の所は万事順調」
「秋月律子の恋愛事情」
「そういうのいいから」
シルバーのピックで種抜きオリーブを突き刺し、律子はそれを口に入れた。噛むと、酸味とオリーブオイルの
香りが口いっぱいに広がった。その表情は怒っているようで、しかし微かに照れているようでもあった。
「意外と、嘘から出た真という可能性だってありますよ?」
「どのくらいの枠が必要ですか?」
律子が男の声を遮る。男はとろけたチーズとミートソースをすくったスプーンを止め、再び手帳に目を遣った。
「正直、そんなに切羽詰っていないので、月刊誌1枠分あれば助かる、って程度ですね」
「話題の賞味期限は? 4週間?」
「いえ、2週間もてば充分です」
「じゃ、『秋月律子、クイズ番組不正疑惑』でどう?」
男はパクリ、とグラタンを口に運んだ。粗挽きの肉の歯触りとナツメグの香りが胃を刺激する。
「私が持ってるノートPCは、あの番組のスポンサーの最新機種だし、実際、正解率も結構なものよ」
「確かにその辺を結べば一枠組めそうです。火消しの材料は、あるんですか?」
律子は輪切りになったラディッシュのピクルスを口に含むと、左目だけつぶって見せた。
「いつも損な役回りですね。秋月さんは」
男が手帳にいくつかのメモを書きながら呟いた。
「ワーカホリックなだけよ」
律子はグラスを傾け、小さく笑った。
男が家に帰ると、時計は21時を指していた。
スーツを脱ぎ、ウォークインクローゼットの中に吊り下げる。その内ポケットから、『三浦あずさ・サマーライブ』の
チケットを取り出す。別れ際、オマケよ、と言って律子が手渡した物だった。
――頑張らない訳には、いきませんね。
男はリビングを抜け、洗面台の正面に立つと、一度丁寧に髭をそり、しっかりと顔を洗った。そして鏡の右の
ラックの中から薄い肌色のシリコン樹脂のベルトを取ると、それを慣れた手つきであごの下に張った。男の顔は
頬のこけた面長の輪郭に変わる。そしてその樹脂の表面には、精巧に作られたナイロン樹脂製の無精髭が生えていた。
男がそうしている間にも、男の携帯には複数のルートから情報が流れ込んでくる。その中には、桂木翔が今、
どこで誰と飲んでいるか、という情報までが含まれていた。
男が全てのメイクを終えると、鏡の中には、40代にしか見えない、暗い目をした男がいた。
男はクローゼットに戻ると、しわの寄ったシャツと色のくすんだジャケットに腕を通し、薄汚れてヨレヨレに
なったトレンチコートを羽織る。そして、黒い安物のネクタイを無造作に首に巻いた。
――さて。じゃ、仕事に入るとしましょうかねぇ。
男は古茶色の帽子を頭に乗せると、気だるそうに首を回した。
夜の街が、これから目を覚まそうという時間だった。
<< 琥珀色のルール >>
『アクアヴィット』という名のバーがある。座席数は35席。渋谷という立地を考えれば、広い方だと言えた。
桂木翔がそこを訪れたのは、部下に、どうしてもあの店の生ハムのピザが食べたいと請われての事だった。
日曜に無理矢理呼び出してシステム誤作動の後始末をさせた技術者の希望とあってはさすがに断りにくく、
経費で落とすつもりで2人の社員を連れてやって来た。
店に入るなり桂木はカウンターの中央に陣取り、自分の左右に2人を座らせる。オーダーはバランタインの17年
をダブル。白州の12年を頼んだ部下を、国産かよ、と笑いながら、小皿の生ハムを指で摘んで口に運んだ。
「けど、大丈夫ですか?」
部下の1人、右側の男が言った。
「あの女、万が一、犬を諦めるって事、無いですかね?」
「そん時はそん時で、どうにでも金にできるさ」
桂木は、スーツの胸ポケットから1枚の写真を取り出した。そこには、桂木の腕に噛み付き、ぶら下がるメイの
姿と、それを必死で止めようとするあずさの姿が写っていた。
「さぁて、金に、なりますかねぇ?」
背後で、そんな声がした。桂木は写真を胸ポケットの中に戻すと、スツールを回してその声の主を探す。ちょうど
真後ろに、その男がいた。薄汚れたジャケットに身を包んだ、野良犬のような表情の男だった。
「口挟むのやめてくんねェかな。目障りだしよォ」
部下の1人、左側の男が言った。その瞬間、真っ白な閃光が男達の目を焼いた。フラッシュだった。
「なっ――!?」
「おやおやぁ? 左右のお兄さんがた、あの日公園にいたサラリーマンの2人組ですよねぇ?」
その一言で、2人の顔色が一変する。平静を装えたのは、桂木1人だけだった。
「アンタ、何者だい?」
「おや、名刺をご所望ですかい?」
男は腰掛けていたソファから立ち上がると、ポケットを2ヶ所、3ヶ所と探り、やっと1枚、むき出しの名刺を
手に取った。右手の人差し指と中指で挟んだまま、桂木の胸元に突き付ける。
「悪徳、又一?」
「ジャーナリスト、ってぇやつですよ」
悪徳は、カウンターの上に置かれた生ハムのピザを一切れ手に取ると、それを裏返してもう1枚のピザに重ね、
サンドイッチのようにして自分の席へと持ち帰る。それを美味そうに齧りながら、グレンフィディック12年を流し込む。
レモンや洋梨に例えられる事の多いフレッシュな芳香が、チーズと生ハムの塩気と上手く合っていた。
「で、ジャーナリストさんが何用ですか?」
桂木の声は怒気を孕んでいたが、悪徳はまるで意に介さずにもう一口、ピザを頬張った。
「いやね、素人さんがアイドルを食い物にしようってぇこの状況に、どうにも我慢できませんでねぇ」
「テメェだって同類だろうがよ」
桂木が吐き捨てるように言った。だが、悪徳は肩をすくめる。
「いぃや、そいつぁ違いますよ。アイドルを食い物にする時ぁねぇ、生かさず殺さずってのが鉄則なんですよ。
アンタ方のやり口はダメだ。乱暴すぎる。このまま進んだって、子犬は死ぬし、三浦あずさは引退だ」
「……アンタ、一体どこまで知ってんだ?」
「何もかも知ってますぜ。あの犬も桂木さん、アンタの仕掛けだ。生まれたばっかりのトイプードルなんてのは
もっと小せぇ。ありゃ、生まれてから半年は経ってる犬だ。躾も訓練も、充分に出来る犬だ」
桂木が、悪徳の声を遮るように声を荒げる。
「何の証拠も、無いだろ!」
「桂木翔さん。アンタと気が合う点が一つだけあるんですよ。いいですよねぇ。『Here we go!!』ってぇ歌は」
悪徳の言葉に、初めて桂木が声を失った。その顔はアルコールを摂取しているにもかかわらず青白い。
「でもね、あんなにいい歌を、悪事に使うのは、どうにもいただけねぇなぁ」
悪徳は懐からスマートフォンを取り出し、データ領域から一つの動画を再生して見せた。狭いコンクリートに
囲まれた部屋の中、秋月律子と、茶色い小型犬の姿があった。
「どこで、撮った……?」
律子は黒く厚い布を右腕に巻いて、その部屋の中で歌を歌っている。『Here we go!!』だ。律子のアカペラが
部屋の中に反響している。歌がサビに差し掛かっても、メイはちょこんと座ったまま、律子の顔をジッと見ていた。
『カッコわらいつけて 涙もきっと暖かいよね』
そして――
『Here we go!! Here we go!! ランデブー』
その瞬間、大きな口を開け、メイが跳躍した。その牙は正確に律子の右腕に突き立てられていた。
桂木は大きなため息をつき、スツールの上で天井を仰ぎ見る。
「フォーカードで勝ちを確信してたかもしれませんがねぇ、トランプのデッキには大抵ジョーカーが2枚入ってる
んです。アンタの抜けてた所は、ジョーカーの在り処に気が回らなかった所ですよ」
カラン、と琥珀色のグラスの中で氷が鳴った。
お前らは帰れ、と、桂木が社員の二人を帰すと、悪徳は自分のグラスを持ってカウンターに移る。
「そういや渋谷の『とあるITベンチャー企業』の不正会計と出資法違反のネタがあるんですが、ご興味あります?
どうにもそこのボンボン社長が、親の七光りを勝手に振りかざしてやりたい放題してるみたいでしてねぇ」
悪徳はグラスの中身を一息で空けると、カウンターの奥のバーテンダーに、この社長さんと同じのを下さいな、
と三杯目のオーダーをした。
<< 運命の輪 >>
あずさは緊張しながら、その電話が鳴るのを待っていた。
まずはメイを保健所から引き取る事。それが最初の、そして最大の目的だった。その後の契約内容については
プロデューサーが再度調整を図る。難航する場合は高木社長が出て話をつける、という所までは決まっていた。
汗で手が滑りそうになる。緊張で喉が渇く。何度も頭の中で繰り返したやり取りが、脳裏で反響する。
月曜、17時。765プロの事務所の電話が鳴った。
「はい、765プロダクションです」
「ああ、えーっと、三浦さんはいらっしゃいますか?」
電話の向こうの相手は想像していたよりも穏やかな口調で、そして安穏とした空気だった。
「は、はい。私が三浦ですが〜」
あずさの雰囲気がいつもの調子に変わったせいで、聞き耳を立てていた765プロの面々にも違和感が伝わった。
亜美と真美はあずさを挟むように座っていたし、雪歩はあずさの向かいで、自分の両拳を握り締めていた。
「ああ、こちら渋谷区保健所ですがねー」
「ほ、保健所さんですか!?」
一瞬、その場にいる全員が息を呑んだ。ただ、そのソファから離れた位置に座る律子が、本のページをめくる
音だけが事務所に響く。
「お宅の犬、被害届けが取り下げられたんですよ。で、引き取りに来て頂けないかと思いましてね」
「――行きます! 今すぐ、行きますっ!」
あずさの声と表情は、事の次第を全て伝えるに充分だった。事務所中に、歓喜の声が広がっていく。改めて
あずさがみんなにその内容を伝えた。行こう、行こうと亜美と真美が立ち上がり、あずさの両手を引っ張る。
プロデューサーはしきりに首を傾げ、
「どうして桂木からの電話じゃなかったんだ? どうして被害届けが――」
と疑問を口にしていたが、律子が渋谷保健所までの地図を手渡しながら、向こうから連絡があったらその時
考えればいいんじゃないですか、と言うと一旦はそれに納得した様子だった。
あずさと亜美、真美、そしてプロデューサーが事務所を出て行き、後には、雪歩と律子だけが残る。
雪歩は、黙ってページをめくり続ける律子の前に立ち、しばらく思案してから口を開いた。
「あ、あの……」
「どうしたの?」
「律子さん、ですよね? きっと、全部律子さんのおかげなんですよね?」
雪歩は尊敬と憧れが重なった表情で律子を見ている。律子は右手を振りながら、
「私にそんな力ある訳無いでしょ」
と言って雪歩の言葉を否定した。けれど雪歩は改めて、深く頭を下げた。
「ありがとうございますっ」
「そういうのいいから」
どこかくすぐったい様な気がして、律子は雪歩に背を向ける。
雪歩には、律子の頬が妙に紅く見えて、それが結局全ての答なんだと思う事にした。
律子は意識を切り替えて、手元のクイズ本に集中する。読ませ押しは得意分野だから、あとはパラレルを磨いて
いこう。なにせ、不正を疑われるくらいの正解率を維持しなくてはいけないのだから。
――さてと、ワーカホリックは伊達じゃないって所を、見せてやるとしますか!
律子の表情は、とても晴れやかだった。
【End】
|


